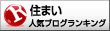回遊動線 間取り
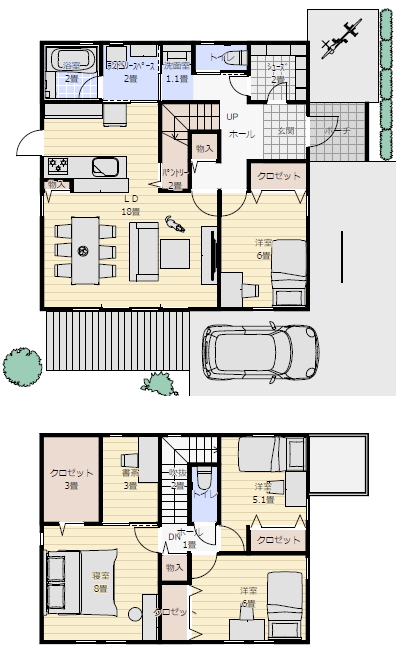
回遊動線 間取り
敷地の大きさ:
12×12M 東道路
建物の規模:
木造二階建て 5LDK 36坪
必要な部屋:
1階
LDK 18畳
洋室 6畳 クロゼット
洗面室1畳 脱衣室 2畳 トイレ1畳
浴室 2畳 1坪タイプ
シューズクローク 2畳
パントリー
廊下物入
2階
寝室 8畳 ウォークインクロゼット3畳
洋室 6畳 クロゼット
洋室 5畳 クロゼット
書斎 3畳
トイレ1畳
駐車場 2台
間取りの要望:
回遊動線の間取り
家事動線の良い家の間取り
帰宅動線の良い家の間取り
シューズクロークはツーウェイドア
洗面と脱衣室は別にする
キッチンから洗濯機の近い
家事動線の良い家
階段は独立階段
2階の寝室のいかっくに書斎
仕切りはあったほうが良い
将来1階で住めるように1階に6畳欲しい
家族構成:夫婦子供3人